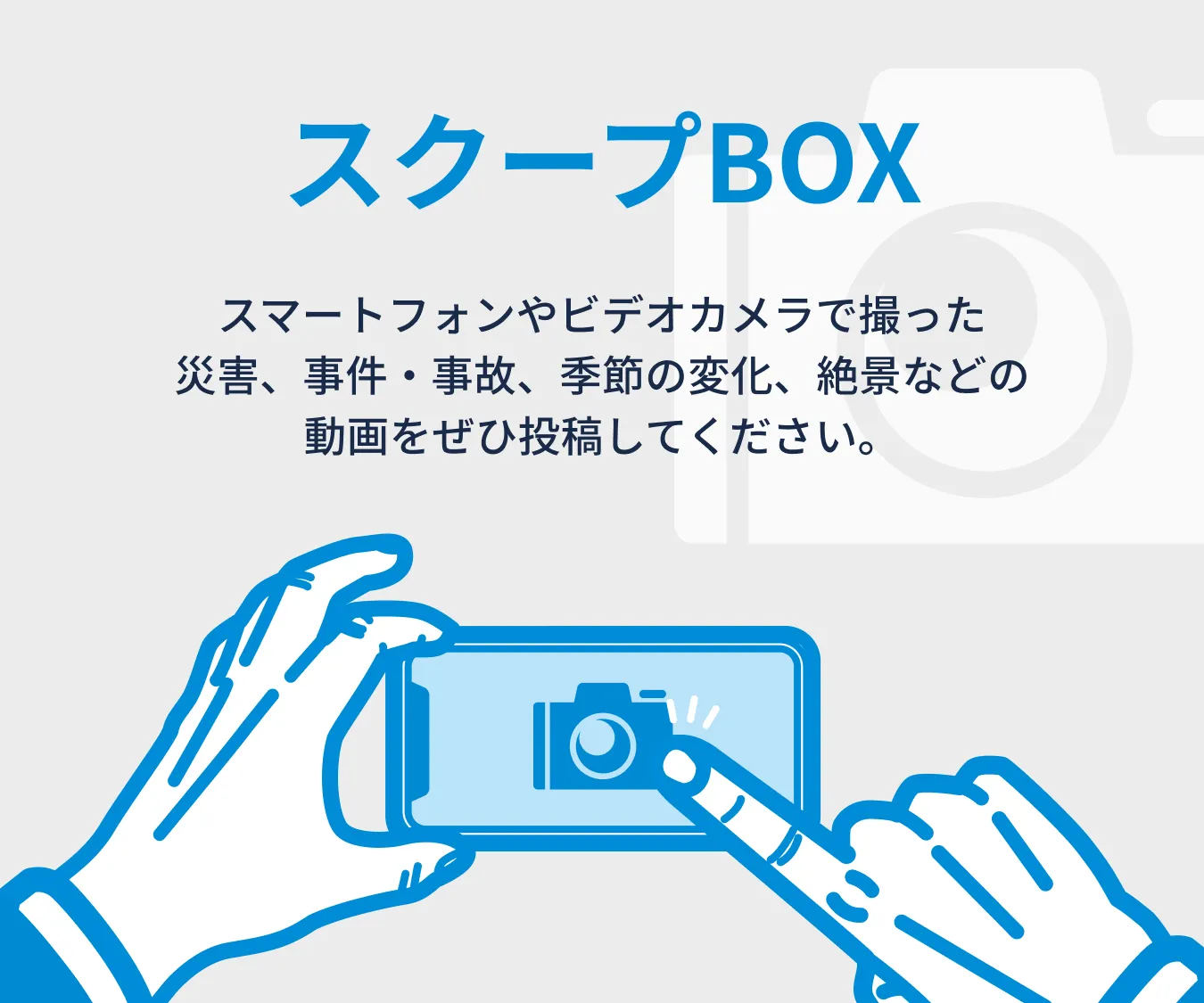ニュース
2025年10月31日(金曜日)
老化の進行の「指標」に たんぱく質の血中濃度 筑波大の研究チーム
筑波大学の関谷元博准教授らの研究グループは、体の代謝に関わる特殊なたんぱく質の血中濃度が、老化や健康状態を判断する指標になるとの研究成果をまとめ、10月30日、記者会見で明らかにしました。この成果は、10月8日に発行された、アメリカの科学誌「ネイチャーエイジング」のオンライン版にも発表されました。研究チームは、生命維持に必要な働きをする代謝物質の「CtBP2」に着目しました。この物質が活性化すると、細胞の外にも分泌され、全身の代謝を改善する働きを見つけました。マウスによる実験では、「CtBP2」を投与されたマウスの寿命が延びたほか、筋力が高くなったということです。「CtBP2」の血中濃度を半日から1日で測定する技術も開発し、調べる期間も短縮できたということです。
長寿家系を調べたところ、「CtBP2」の血中濃度が高い傾向にありました。糖尿病患者では、心臓や腎臓で合併症が起きると「CtBP2」の血中濃度が低くなりました。「CtBP2」の血中濃度を合併症の発生リスクを判断する指標にすれば、必要な人に医薬品を適切に処方できるなどの応用が期待され、効率的な医療の提供に貢献できる可能性があります。さらに、新たな老化防止薬の開発につなげたい考えです。